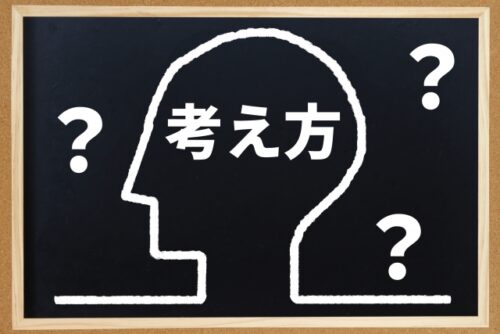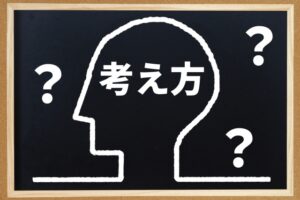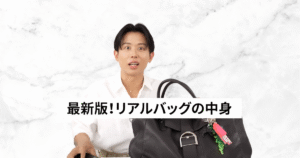アイデアを生むのは簡単なようで難しい。特に、日常の仕事やプロジェクトで「新しいアイデアが必要だ」と言われたとき、多くの人はプレッシャーを感じます。
そんなときに試してみてほしいのが、「問題逆転」という発想法です。この手法は、チャールズ・トンプソンによって開発され、発想の狭さに気づかせる「簡易ゲージ」としても活用できます。このブログでは、問題逆転の手法がどのようにしてアイデアを生むのか、そのプロセスと具体的な活用法をご紹介します。
| ステップ | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| ステップ1 問題の言語化 | 問題や課題、既存のアイデアを明確に言葉で表現する。 | 売上が足りない |
| ステップ2 問題の逆転 | 言語化した問題の一部を否定形や対義語に置き換える。 | 売上が多すぎる |
| ステップ3 逆転解決策の考案 | 裏返した問題に対する解決策を考える。 | 売上を減らす案を考える<br>(例:売り渋る、自らネガティブ広告を打つ) |
| ステップ4 元の問題への適用 | 逆転解決策を元の問題に適用できないか考える。 | 売り渋る→期間限定や地域限定で販売し、プレミアム感を出す |
| ステップ5 解決策の確認 | ステップ4で考えた解決策が実際に使えるかどうかを確認する。 | 実際に期間限定販売を行い、売上が上がるかテストする |

ポイント
- ステップ3では、逆転した問題に対する解決策を考える際に、他の技法(ブレインストーミング、SWOT分析など)を併用するとより多くのアイデアが出る可能性があります。
- ステップ4では、逆転解決策を元の問題にどう適用するかを考える際、一部を変更することで新しい視点や解決策が見えることがあります。
- ステップ5は実験的なフェーズであり、ここで得られたデータやフィードバックを元に、解決策を調整することが重要です。

問題逆転の事例について

おとり捜査:問題解決の新しい視点
警察の仕事といえば、犯罪者を見つけて逮捕することが一般的ですよね。でも、おとり捜査はその常識を180度変えています。
逆転のサスペンス
通常、警察は犯罪者を特定し、その居所を突き止め、逮捕に向かいます。でも、おとり捜査では全く逆。犯罪者を特定もしない、居所を突き止めもしない、そして何より警察が動くのではなく、犯罪者に動いてもらいます。そう、まるでドラマのような逆転が起こるんです。
防犯の新常識
警察は普段、犯罪が起きないように防犯活動をします。でも、おとり捜査では逆。警察自らが犯罪の「きっかけ」を作り出します。なぜなら、それが犯罪者を引っかけるための最も効果的な方法だからです。
潜在的な問題、解決!
このような逆転の発想は、実は潜在的な問題に対する新しい解決策を生み出しています。犯罪者が警戒心を持っている場合、普通の方法ではなかなか逮捕できません。でも、おとり捜査なら、犯罪者自らが警察に近づいてくれる。つまり、逮捕がぐっと楽になるわけです。

失敗を意図的に作る:問題逆転の力

なぜわざわざ失敗を作るのか?
多くの人が成功を追求する中で、失敗は避けたいものとされています。しかし、問題逆転の手法を用いると、失敗にも価値があることが明らかになります。
まとめ

思考のバランスを崩すことの価値
問題逆転は、我々の「通常運転」を崩す力を持っています。その結果、新しい疑問や視点が生まれ、より創造的な解決策に繋がる可能性が高まります。
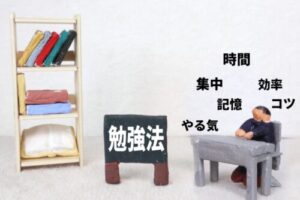
無料で使える人気サービス>
【動画&音楽 使い放題】
学生限定 Amazon「Prime Student」
【6ヶ月無料】
【音楽聴き放題】
Amazon「Music Unlimited」
【30日間無料】
【本の聴き放題】
Amazon「audible」
【30日間無料】